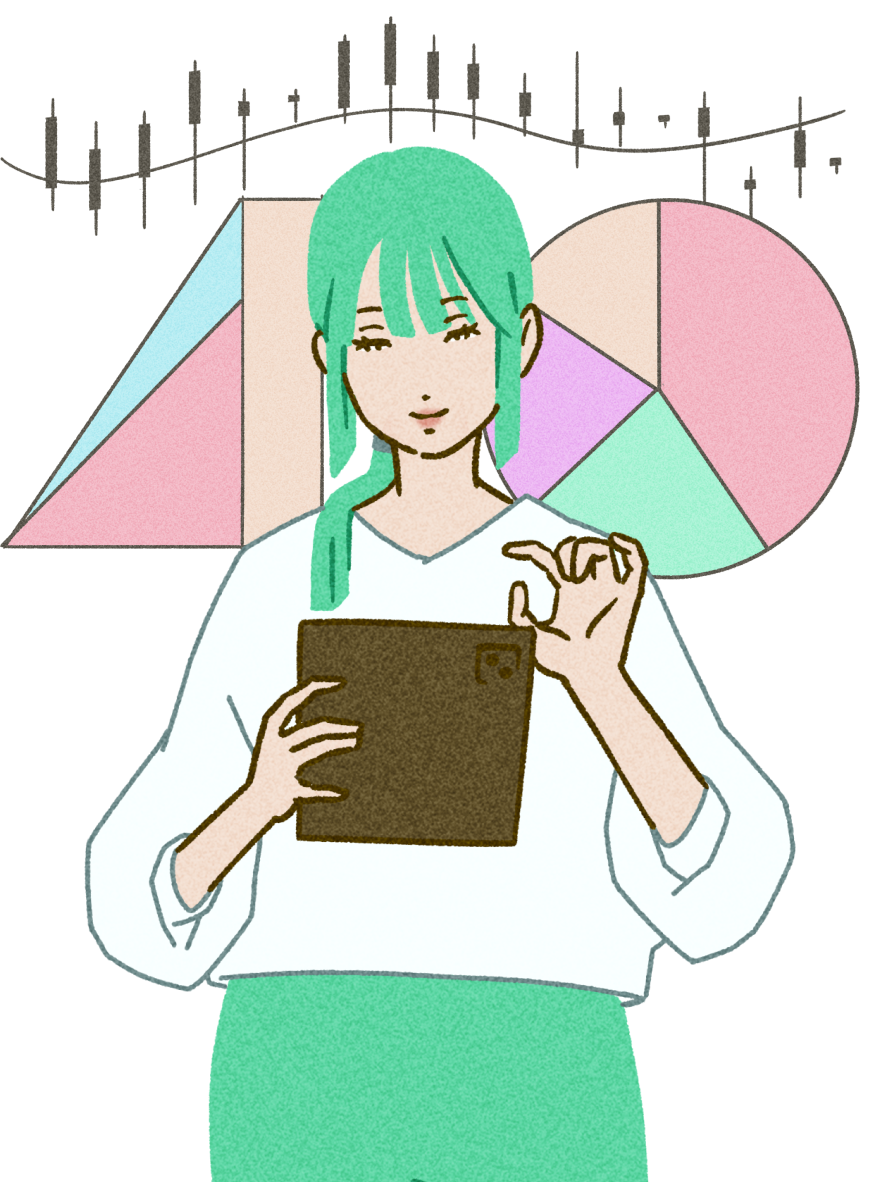
年金業務
提案し、運用・運営・管理で支える。
企業年金のあり方に多様性を。
企業も労働者も「選べる」ことが日本社会をもっと柔軟に豊かにする。
高度経済成長のような右肩上がりの経済や、高い運用利回りを前提とした企業年金は社会環境の変化により持続困難となり、新たなシステムが模索されました。それが、「確定給付企業年金」と「確定拠出年金」という2種類の企業年金制度です。給付額をあらかじめ決めておく「確定給付企業年金」と、運用に拠出する金額を決めておいて運用方法は従業員の側が選ぶことのできる「確定拠出年金」の2種類を企業は選択できることになりましたが、そのどちらを選ぶことがよいのか、または2種類をどのような配分で組み合わせるかは、企業の経営状況により異なります。我々は、お客さま企業の従業員の人数、年齢構成、それらを基にした年金の財政運営を分析し、企業の財務戦略を踏まえた提案を行います。また2種類の年金制度の配分ごとに財務影響等の将来シミュレーションも行います。そのうえでお客さまに選択のための判断材料を様々な視点から提供し、お客さまと一緒に制度設計を考えます。
少子高齢化が進む現在、企業年金は公的年金と並び従業員の老後を支える重要な存在です。だからこそ企業年金をどう設計・運用するかは従業員に対する企業姿勢を表すものといえます。採用マーケットにおいて優秀な人材から選ばれる企業であるべく、企業年金の制度設計や運用はますます重要性を増しています。また逆に従業員の側からすると、確定給付企業年金で給付の安定を望むか、確定拠出年金で運用の自由度を手に入れるかはライフスタイルの設計に大きく影響します。企業も従業員も選択肢が増えれば増えるほど、多様性が確保でき、日本社会はより柔軟に豊かになるでしょう。我々は、コンサルティングから運用、そしてデジタル化も含めた業務受託までワンストップで提供できる基盤を生かし、企業経営やライフスタイルの多様性確保に貢献し、持続可能な柔軟な社会の実現に貢献していきます。
業務内容と取り組み
業務受託・運用
・確定給付企業年金 お客さま企業からお預かりした掛金を総合的に管理します。当社にて運用を行うとともに、従業員一人ひとりへの給付額や時期などを計算・管理しつつ給付業務を代行します。ただし年金特定信託の場合は、投資顧問へ運用委託し、当社はその資産管理のみを行います。
・確定拠出年金 受託者としてお客さま企業の従業員から掛金を預かり運用会社へ委託。その資産管理を行います。受給者への給付金の送金や納税事務も実施します。
年金コンサルティング
年金制度を実施する事業主等は、加入者等の受給権を保護するため、安全かつ効率的に年金資産の運用を行わなければなりません。そのためには、年金ALM(Asset Liability Management)分析に基づく年金制度の将来像を踏まえたうえでの年金資産・負債の総合的な管理が必要です。
また、運用におけるポートフォリオのコンサルティングや、制度に関するコンサルティングなどを通じ、企業の長期的な年金制度運営をお手伝いしています。
社会変化に応えた進化
企業の年金を運用代行する。
日本には元々退職一時金という制度が普及していましたが、それを毎月の掛金へと平準化する企業年金という考え方が生まれました。
戦後、高齢化と核家族化が進む中で老後の生活保障に対するニーズが一段と強くなりました。一方、企業内部においては従業員数の増加と給与水準の上昇により、将来の退職一時金が多額になることは避けられず、退職一時金の年金化が求められるようになったのです。
企業年金の第一号は1949年、ある大手百貨店といわれています。その後次第に注目を集め、高度経済成長期の高い金利や平均寿命が伸びる中、老後の生活保障という従業員側のニーズとも合致し、普及していきました。
企業の都合や労働者の要望に応えて国が制度として認め、年金原資として企業の拠出する掛金を損金扱いとするなどの税制改正が行われ、1962年には税制適格退職年金制度が発足しました。税制上の措置が講ぜられたこともあって、適格退職年金制度は企業の従業員福祉対策の一環として注目を集めましたがこの制度の設計には難解な面もあり、当社はその信託型の設計を解説した『信託型企業年金の設計』を刊行し、個別に制度設計の相談に乗りました。これは当社の年金におけるコンサルティングの端緒でもあります。
新たな年金制度をパートナーとしてともに構築する。
1962年に誕生した適格退職年金制度に加え、1966年に発足した厚生年金基金制度により、企業年金はますます普及し、公的年金とともに社会に根づいていきました。しかし1990年のバブル崩壊により高い運用利回りに陰りが見え、運用成績が悪化しました。日本経済の地盤沈下とともに、本来必要な年金の原資がきちんと準備されない企業も増えていったのです。
2001年には適格退職年金の10年後廃止が決定されるとともに、それに代わるものとして確定給付企業年金制度および確定拠出年金制度が発足し、企業年金は主にこの2制度の選択となりました。1960年代の企業年金黎明期と同様、新たな制度設計には複雑さと困難さが伴うため、我々は率先してそのコンサルティングに取り組みました。その後も制度の整備や変更が進む中、企業のパートナーとして年金部門は伴走を続けています。
年金のあり方が、企業の価値を決める。
企業と社員の信頼関係を構築する。
高齢者人口が全体の約3割を占め、世界的にも有数の高齢化先進国である日本。老後の生活保障の模索は続いています。また、企業年金をはじめとした福利厚生制度は若者が企業選びを行う際の判断材料の一つとして重視されるようになっています。企業年金とは福祉の手段であるとともに、企業価値を左右するもの。従業員に対して誠実か、生活保障に対する多様性があるか、持続可能か。ESG投資も注目される現代において、年金を通じた企業価値の向上、そして持続可能な社会への貢献こそが私たちの使命だと考えています。
